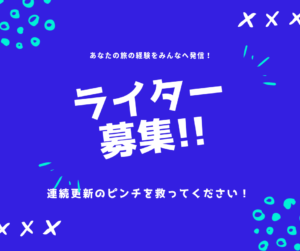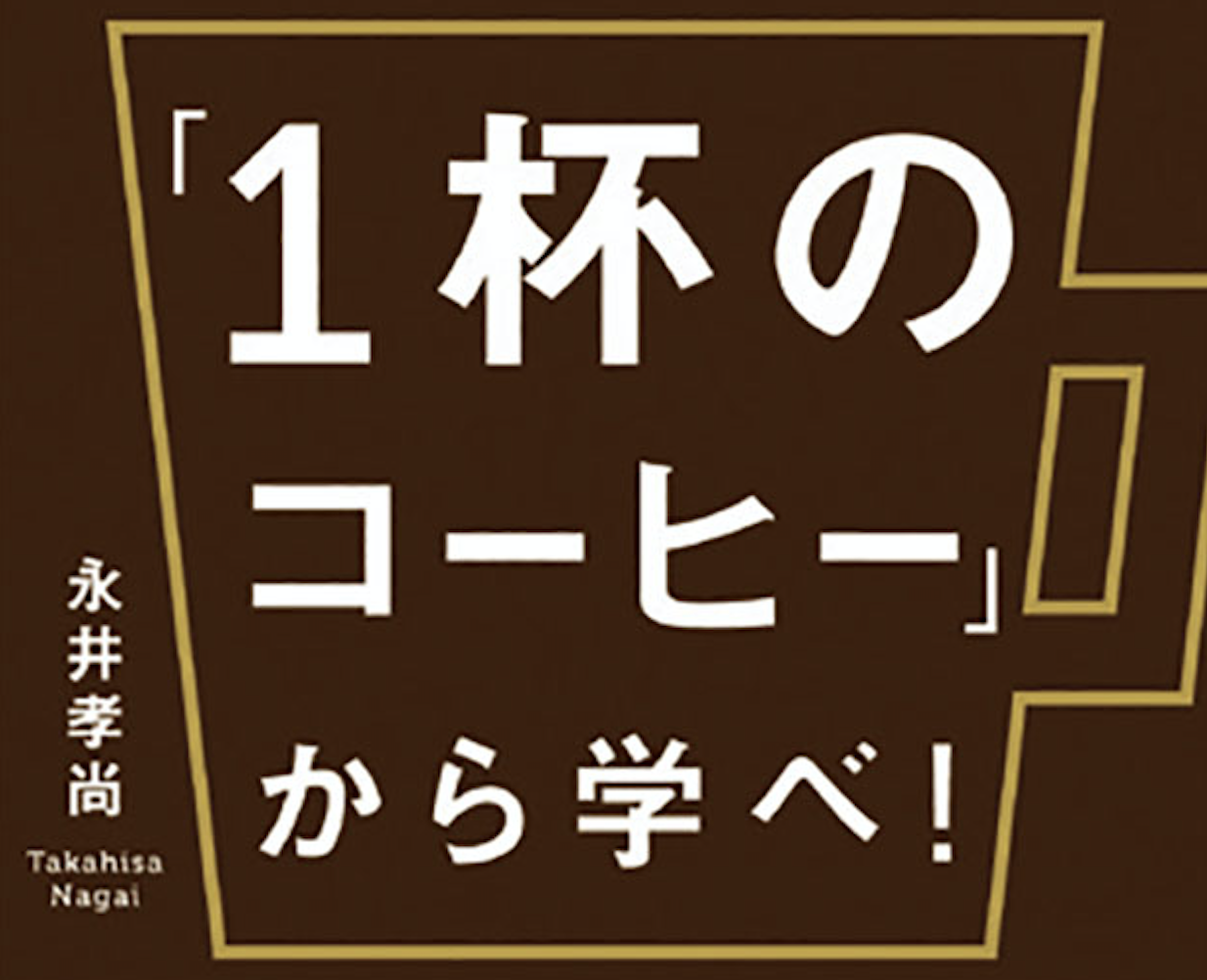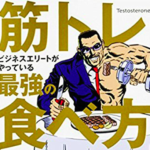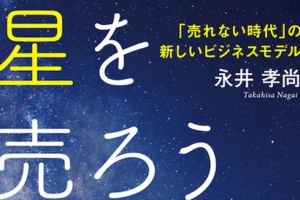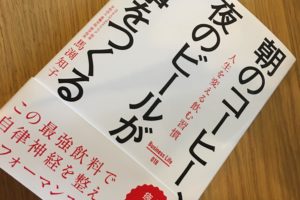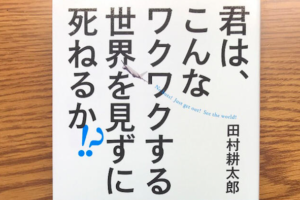今個人的ではありますが、永井孝尚さんの本にハマってしまい新年から読み漁っております。
永井さんはコミック版 100円のコーラを1000円で売る方法で有名な方です。こちらは3部作でており、コミック版まで発売されています。
前に読んだ本を記事でも紹介していますが、まだの方はどうぞ。
こちらの本があまりに読みやすく分かりやすかったので、2冊目に手を伸ばした次第です。
ということで、今回も役に立った部分をシェアしていきますね。
戦略は一杯のコーヒーから学べ!
コーヒーが好きな僕はタイトルからそそられました。
こちらですね。
そうだ、星を売ろう 「売れない時代」の新しいビジネスモデル と同じく、最新のビジネス情報が物語形式で分かりやすく展開されています。まずここがすごいことで、かなり分かりやすいんです。
主人公であるさくらは、前の会社を逃げるように退社し、とある喫茶店がきっかけでコーヒー会社に入社することになります。そこからコーヒー業界の様々な知識を学んでいくんですが、なんとビジネス戦略の宝庫だったんです。
「外資系のスタバ、異業種のセブン、マクドナルド、ドトールの価格競争、最大手ネスレのイノベーションなど、超強力ライバルを相手にどう生き残っていくのか」と物語は進んでいきます。
ドトールの低価格戦略
ただ値段を下げればいいってもんじゃない。(コンビニの100円コーヒーには勝てない)
ドトールは従来提供している価値に「何を加え(足し算)」「何を捨て(引き算)」「何を増やし」「何を減らす」かを明確にした。
— リュウ (@laugfull) 2018年1月8日
まとめるとこうです。
増やす→利便性(注文してすぐに出てくる)
減らす→滞在時間(立ち飲み)
付け加える→大幅な低価格(300円→150円)
取り除く→フルサービスを廃止してセルフサービスに
さらに
スタッフの人数を変えずに、コーヒーの値段を半額にしても、4倍のお客が来れば売上は2倍。そのためにはどうすればいいか。
— リュウ (@laugfull) 2018年1月8日
そのために機械への投資も行なっています→少ない人数で回せるように
ネスレのジレットモデル
例えばネスカフェアンバサダー。製品本体を安く提供することにより、それに伴う専用の消耗品で売り上げを立てる。ユーザー数と比例してリピート(毎月の購入量)も増える。しかも安定的に収益を見込める。素晴らしい仕組みですね。
ジレットモデル=消耗品で儲けるビジネスモデル(例:インク、ネスカフェアンバサダー、専用替え刃等)
製品本体を安く売っても(もしくは無料)、ユーザーを大量に抱え込むことができれば、消耗品の儲けで回収できる。
— リュウ (@laugfull) 2018年1月8日
僕たちが気づかないところで、実は様々な戦略が繰り広げられています。
UCCの缶コーヒー成功の秘密
「缶コーヒーなんて邪道。コーヒーとして認めない」時代に、缶コーヒーの販売を諦めなかったUCC。
顧客に何が欲しいかを聞いて、その通りに作っても、顧客のためになるとは限らない。隠れたニーズは、顧客に聞いても分からない。顧客自身も気づいてないからだ。
→徹底的に顧客になりきり、顧客の立場で考え気持ちを理解する。
— リュウ (@laugfull) 2018年1月8日
それまでのコーヒー牛乳の顧客は、「牛乳スタンドで飲む」客だった。しかし、UCCは「どこでも飲める」という顧客の隠れたニーズを見つけ出し、果敢に挑戦した。
その結果、8000億円もの市場を新たに創造した。
5度目の正直、セブンカフェ
僕もこの本で初めて知ったんですが、「セブンイレブンは1980年代からすでに30年以上、店内でコーヒーを出すことにしつこく挑戦してきた。今回5度目の挑戦で、ようやく念願が叶った」とのこと。
セブンイレブンの真骨頂は、仮説検証を愚直に繰り返すこと。仮説を立て、実行し、検証して、そこから得た学びを次に活かす。→その結果、セブンカフェが大ヒット。
— リュウ (@laugfull) 2018年1月8日
全国約16000店舗から集められた膨大の量の顧客情報を元に、仮説検証を繰り返してきた。その結果、あのセブンカフェが誕生。
自社らしさを常に問い続ける
主人公さくらは上司の藤岡から、常に「自社(ドリームコーヒー)らしさとは何か?」を問われます。物語の中でもこの部分に一番フォーカスされており、さくらは一生懸命に答えを導きだします。
❶自社ならではの強みは何か?
❷その強みを必要とするお客様は誰か?
❸そのお客様は何を必要としているか?
❹お客様が自社を選ぶためには、どうすればいい?常に問い続ける。
— リュウ (@laugfull) 2018年1月8日
これは自分にも当てはめられますね。例えば「このラーフルの強みは何か?」「ラーフルの強みを必要とするお客様は誰か?」
「コーヒー好きのお客様に美味しいコーヒーを低価格で提供する」
↑典型的なダメな例。こんなのは当たり前でどの会社もやっている。
→もっとターゲットを絞り込み、具体的に「こういう人」というとこまで落とし込む。そうでなければ他社との差別化もできない。
— リュウ (@laugfull) 2018年1月8日
そこでもう一度、自社らしさとは、顧客に本当に提供したいものは?を考えさせられます。
そもそも製品とは、3つのレベルから成り立っている。「❶中核」「❷実体」「❸付随機能」だ。
❶顧客が本当に買っているものは?
❷そして実際に提供されているものは?
❸最後に安全な価値を提供するために必要なものは?— リュウ (@laugfull) 2018年1月8日
そして製品の本質を学んでいくさくら。
当たり前のものに目を向ける
今回の本を読んで思ったことは、僕らが当たり前のように使っているサービスや物は、実は企業による絶え間ない努力の結晶ということ。
缶コーヒーやセブンの100円コーヒーも、実は様々な戦略や失敗が積み重なってできたということ。一つ視点を変えて物事を見るだけでも、色んな発見を見つけることができます。
コーヒー業界を舞台にどんどん成長していくさくらのように、日々に疑問と学びを持って生きていきたいですね。
自分や自社に当てはめて使える戦略も多々あり、本当に学びのある1冊です。
また物語形式なのであっという間に読めますよ。
気になった方はこちらからどうぞ!
最後に、著者の永井さんからコメントが、、!!!
お読みいただき有り難うございます! https://t.co/FM4i6DT0q4
— 永井孝尚 (@takahisanagai) 2018年1月8日
こんなことってあるんですね〜。感激しました。。
発信は大事だと改めて考えさせられました!